早生まれの不安を“推し活”が吹き飛ばしてくれる!?
早生まれの子を育てていると、どうしても「他の子より発達がゆっくりかも…」「比べてしまって不安」になってしまいます。
でも実は、早生まれの子こそ“好き”や“推し”を育てることが、個性を伸ばす最良の方法なんです。
興味の移り変わりが早いのは、武器になる
幼い子どもは、どんどん興味の対象が変わっていくものです。
我が子も、アンパンマン→おかあさんといっしょ→ニチアサと、どれも1年続かずに“卒業”。
けれど、パパやママが大好きなジャンルにはずっと興味を持ち続けています。
大人から見ると「飽きっぽい」と見えるその姿は、裏を返せばたくさんの情報を吸収し、取捨選択する力が育っている証拠。
早くから「自分の好き」を探すチャンスに恵まれているのは、むしろ強みです。
競争ではなく「自分だけの選択」を
これからの時代、必要とされるのは「偏差値の高い人生」だけではありません。
・好きなことに夢中になれる
・自分の感性を信じられる
・周囲と違っても気にせず選べる
こうした力は、テストの点数や運動の速さでは測れない、人生を支える“土台”になります。
特に早生まれの子は、月齢の差で「できない」と思われがちですが、比べるべきは“誰か”ではなく“過去の自分“です。
「ダークホース」が活躍する時代
近年注目されているのが、後から力を伸ばし、型破りな成功をする「ダークホース」型の人材。
レースの序盤では目立たないけれど、自分のタイミングで、一気にブレイクスルーする力を持つ人たちです。
そんな子に共通するのは、「誰かに与えられた課題」ではなく、“自分で選んだ好きなこと”に打ち込んだ経験があること。
今はまだ遊びに見えるような「推し活」も、子どもの自己肯定感や表現力を育て、将来の原動力になってくれるはずです。
好きなことにハマる体験は、一生の宝になる
勉強や受験が大切なのは事実です。
でも、それだけが子どもの未来を決めるわけではありません。
「好きなことに夢中になれる子」は、
・失敗しても立ち直る力
・探求する力
・工夫する力
を自然と身につけていきます。
「うちの子、ちょっとマイペースかも?」と感じたら、その特性を生かして“推し”を見つけてあげるのが近道かもしれません。
特に早生まれの子には、「好き」を付き進める事で、学びや育ちの大きな一歩になります。
周りと違っても、焦らず、ゆっくりで大丈夫。
「推しがいる子は強い」
Switchで“推し”を楽しむ|あつ森が育児に最適な理由
Nintendo Switchのゲーム「あつまれ どうぶつの森」は、大人にとっても癒しのゲームですが、実は育児にもぴったりのツールです。
我が家では、2歳のころからママのアカウントで一緒に遊びはじめ、今では自分で起動して操作するほどになりました。
ゲームの中での体験は、子どもの五感や好奇心を刺激します。
例えば…
- ファッションで個性を表現する
私なら絶対に選ばないような奇抜な服装や色の組み合わせも、子どもにとっては自由な表現の場。誰の目も気にせず「自分らしさ」を楽しんでいます。 - 名前を覚える、探す、育てる
虫や魚の名前を覚えたり、季節ごとの変化を楽しんだり、畑で育てた野菜で料理を作ったりと、遊びの中に“学び”の要素がたくさん詰まっています。 - 社会のルールや仕組みを知る
買い物をしたり、ローンを返済したりといったゲーム内の「仕組み」は、お金や時間の使い方の感覚を自然と学ぶことにもつながります。
このように、ただの遊びに見えても「あつ森」は自己表現・言葉の発達・知的好奇心を育む教材にもなり得るのです。

Nintendo Switch「あつまれどうぶつの森」で遊ぶ写真の一部

「早生まれ 子育て」は“遅れている”のではなく“個性が違う”だけ
早生まれの子は、学年の中で月齢が一番低いため、どうしても身体的・精神的な成長が周囲と比較されがちです。
でもこれは、“発達が遅れている”のではなく、“発達のタイミングが違う”だけの話。
特に幼児期は、わずか数ヶ月の差が大きく見える時期です。
焦らず、その子のペースを見守ることが重要です。
「3月生まれの子は、4月生まれの子に比べて、11ヶ月脳みそが若い状態で始める事が出来る」
私はこの言葉を常に頭の片隅に置いています。
「子連れ推し活」で自己肯定感と表現力が育つ
「子連れ推し活」とは、親が楽しんでいる“推し”を、子どもと一緒に楽しむこと。
たとえば、我が家では…
- ママの推し(ゲーム・サンリオ・刀剣乱舞)を一緒に楽しむ
- パパの推し(野球・アイドル)の曲で自然と踊るようになる
- Switchを2歳から触って、今では自分で“あつ森”を操作する
こうした日常のなかで、
「推し活を一緒にする=自己表現と共感を学ぶ時間」になるのです。
「これが好きなんだね」と親が言葉にしてあげることは、「好きなものを好きって言っていい」と思える力に変わります。
どんな推し活がある?
「推し活」と聞くと、ライブやイベントなど大人向けのイメージがあるかもしれませんが、実は年齢に合った推し活がたくさんあります。
早生まれの子は、月齢の差で体力面や集団行動でハンデを感じやすいこともありますが、感受性が豊かで、じっくり自分の世界に浸るのが得意な子が多い傾向があります。
そんな特性を活かせる推し活をいくつかご紹介します。
おうちでできる「やさしい推し活」
- アニメやキャラクター作品を一緒に楽しむ
サンリオ、プリキュア、戦隊ヒーロー、ポケモンなど、親子で“好き”を共有しやすいジャンルからスタート。会話のきっかけにもなります。 - ぬいぐるみやフィギュアを使ったごっこ遊び
「推しキャラと暮らす」設定でのごっこ遊びは、想像力と感情表現を育てるのに最適です。 - 推しの塗り絵や工作を一緒にする
好きなキャラをテーマにしたお絵描きや折り紙、簡単な手作りグッズなども、「自分の好き」に触れながら手先を使う練習に。
外に出て楽しむ「体験型推し活」
- テーマパークや展示会など、好きな世界に“会いに行く”
サンリオピューロランド、ハーモニーランド、キャラクター展覧会など、推しの世界観をリアルに体験することが、感性を大きく刺激します。 - パパママの“推し活”に同行して共感する
ライブやスポーツ観戦はまだ早いと思うかもしれませんが、親が楽しんでいる姿を一緒に感じることは、「好きに夢中になっていいんだ」という自己肯定感につながります。
このように、早生まれの子には「無理なく楽しめて、自己表現につながる」推し活を取り入れることがポイントです。
周囲と比べて焦るよりも、その子のペースで“好き”を深めていける時間こそが、一番の伸びしろになります。
まとめ|「早生まれ×子連れ推し活」は、これからの教育スタイル
子どもは、誰かと比べるものではなく、「自分の人生を楽しむ力」を育てていく存在です。
「周囲に遅れてる…」と感じやすい早生まれの子こそ、
推し活を通じて、好きなものを追いかける喜びを知ってほしい。
それが、
- 学びの土台となる好奇心
- 他人と比べず自分を信じる力
型にはまらない“ダークホース”としての可能性を育てる第一歩になります。
おすすめ記事
- 「子連れ推し活って何?」と感じた方へ
→ 子連れ推し旅で叶えた、私の幸せ時間|幼児連れでも諦めない推し活のコツ - 我が家は「ハーモニーランド」が主戦場♡
→ 子連れで行くハーモニーランド|幼児も楽しめるスポットまとめ - 子連れ推し旅をするには、前準備がとっても大切
→ 子連れ旅行のためのキャンセル保険の重要性|幼児連れ推し活も安心
→ 子連れ推し旅をもっと楽しくするための持ち物リスト
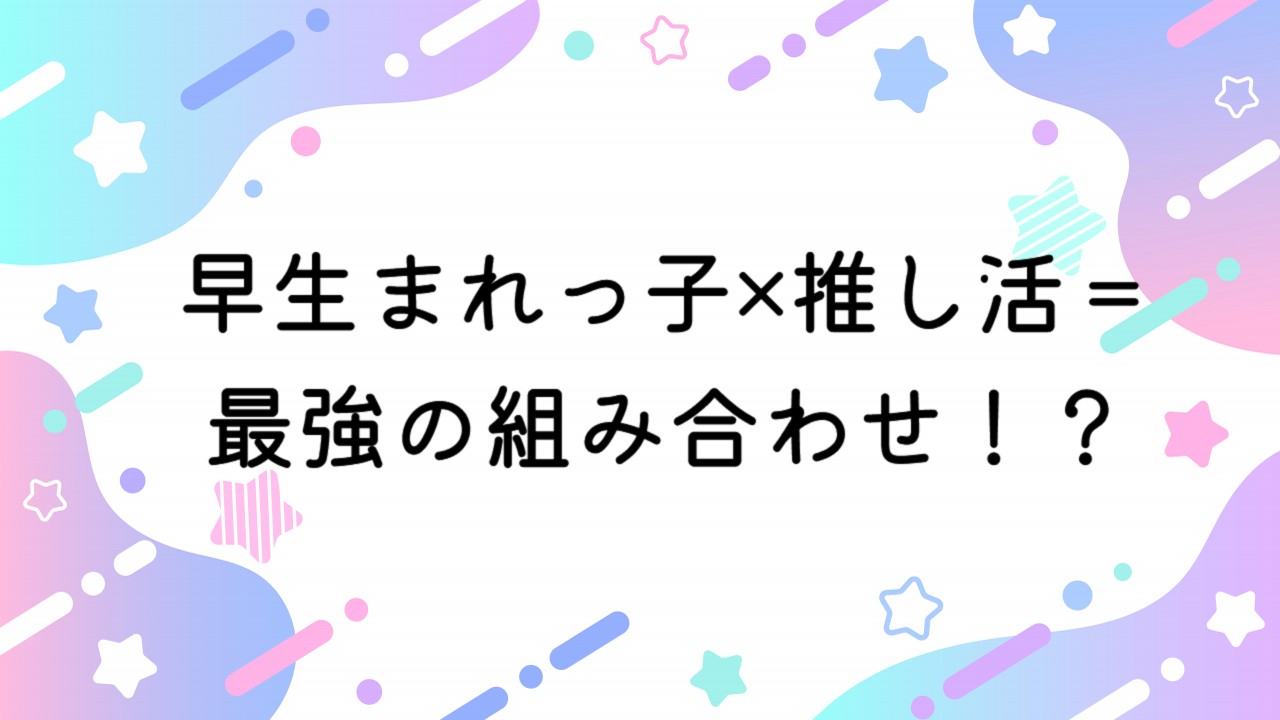

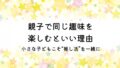
コメント