
親の趣味に子どもを巻き込むのはどうなんだろう?
実は、親子で同じ“推し”や趣味を共有することは、子どもの発達にも、親子関係にも、たくさんの良い影響をもたらします。
今回は、子どもが小さいうちから親と一緒に“推し活”を楽しむことのメリットについてお話しします。
子どもの「好き」は親から始まる|子連れ推し活が育む好奇心
子どもがまだ幼い時期、本人の「好き」がまだ明確でないこともよくあります。
それは当然のこと。
生まれてまだ数年しか経っておらず、世の中の選択肢を十分に知らないからです。
そんな時こそ、親の“好き”を共有する「子連れ推し活」が効果的です。
たとえば我が家では…
- ママの「サンリオ」愛や「刀剣乱舞」愛に、子どもも自然と興味を持ち、
- パパの好きな「野球」や「アイドル」にも反応するようになりました。
大の人見知りで内気ですが、足はクラスでも早い方で、ダンスが大好きです。
今は「CANDY TUNEの倍倍FIGHT!」がお気に入りです。
親の“好き”は意外と長続きする|我が子の反応からわかったこと
我が子はこれまで、「アンパンマン」「おかあさんといっしょ」「ニチアサ」といった子ども向けコンテンツにも触れてきました。
でも、それぞれにハマった期間はどれも一年未満。
一時的なブームで終わってしまいました。
アンパンマンミュージアムに行く計画を立てた頃には、興味を失っており、子どもに行くか尋ねたところ「行かない」と言われたのは記憶に新しいです。
ところが、ママとパパが好きなもの——
- 「サンリオ」や「刀剣乱舞」(ママ)
- 「野球」や「アイドル」(パパ)
これらには、ずっと変わらず興味を示してくれているのです。
もしかすると、単純に子どもの趣味に合っただけかもしれません。
でも、「親が楽しんでいる姿に触れ続けたこと」が、その興味を育ててくれたのではないかと実感しています。
単純接触効果を活かそう|家に“推し”があると子どもは育つ
心理学では「単純接触効果」という言葉があります。
これは、何度も接したものに人は好感を抱くという効果のことです。
たとえば…
- 家に「宇宙図鑑」があると、子どもは宇宙に興味を持つ
- よく見るアニメのキャラを自然と好きになる
このように、親が“推し活”で触れるものが家の中にあるだけで、子どもは刺激を受けて育ちます。
親子で同じ趣味=会話が増える|学力や情緒面にも好影響
親子で“推し”を共有していると、自然と会話が生まれます。
- 「今度はこんなグッズが出るらしいよ」
- 「この曲好き? もう一回聞く?」
- 「一緒にイベント行こうか」
こうした日常のやりとりが、子どもの言語力や表現力を育てるだけでなく、学力向上にもつながると言われています。
また、共通の話題があることで親子の距離がぐっと縮まり、子どもにとっては「自分の話を聞いてもらえている」「理解してくれている」という安心感が得られます。
これが情緒の安定や自己肯定感の向上につながるのです。
たとえば、
- 新しい推しグッズの名前を覚えたことで語彙力が増える
- ライブ映像を見ながら気持ちを言葉で表す機会が増える
- 一緒にイベントに行く計画を立てる中で、時間の感覚や計画性が育つ
これらは、学校の勉強とは違うけれど、確かに“学び”につながる体験です。
「好き」を通じた親子のコミュニケーションは、心を育てるだけでなく、生きる力の基礎をつくっているのかもしれません。
親の真似は子どもの基本|推し活は“模倣”を活かす絶好の機会
子どもは親の行動をよく見ています。
怒った時の口調を真似された経験、ある方も多いのではないでしょうか。
この“模倣”の力を、ポジティブな方向に活かすのが「子連れ推し活」です。
- 親が楽しんでいるゲームに興味を持つ
- 一緒に歌ったり、踊ったりして遊ぶ
- 推しグッズを大切にする様子を見て、物を大事に扱うようになる
親が夢中になっている姿こそ、子どもにとっての学びなのです。
実際、文部科学省が推進する「家庭教育支援施策」では、家庭での親子の対話が学力や自己肯定感の形成に重要な役割を果たすことが明記されています(※1)。
また、アメリカの心理学者バンデューラによる社会的学習理論でも、「身近な大人が楽しんでいる行動を子どもが模倣し、その過程で学習が進む」と説明されています(※2)。
共通の話題があることで親子の距離がぐっと縮まり、子どもにとっては「自分の話を聞いてもらえている」「理解してくれている」という安心感や信頼感が育ちます。
これが情緒の安定や自己肯定感の向上につながるのです。
※1 文部科学省「家庭教育の再生に向けて(家庭教育支援施策の方向性)」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/katei/04060901.htm
※2 Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
無理してお出かけするより、家で一緒に推し活する幸せ
「休日は子どものために外出しなきゃ」とプレッシャーを感じる親御さんも多いはず。
でも、疲れた体に鞭を打って人混みに出かけるよりも、親子で“推し活”する休日の方が、ずっと有意義かもしれません。
- 家で推しキャラの動画を見る
- 一緒にグッズを作ってみる
- 親が好きな曲をかけて、一緒に踊る
こうした時間が、子どもにとっても親にとっても心の栄養になります。
推し活は才能の種になる|夢中になった経験が未来をつくる
「何かに夢中になった経験」は、その後の学びや才能に直結します。
推し活を通じて、子どもは“好きなものを深める楽しさ”を知ります。
例えば我が家では…
- アイドルの曲が流れると、遊びをやめて踊りだす
- 「ママのゲーム」と言いながら一緒にプレイしてくれる姿
こうした姿は、子どもの感性や個性を育てる第一歩です。
“あつ森”が教えてくれた!子どもとテレビゲームを楽しむための工夫
我が家では、パパもママもゲーマーなので、Nintendo Switchは2歳ごろから触らせています。
今では一人で『あつまれ どうぶつの森』を遊ぶことも。『スプラトゥーン』や『マリオシリーズ』も人気ですよね。
まだママのアカウントですが、すでに子ども専用のアカウントも作成済みで、島に“移住”する準備は万端です。
もちろん、ルールは最初から明確に設定しています。
「遊ぶ時間」「終わるタイミング」「片付けること」は繰り返し伝え、
「ごはんだよ、終わりにしてね」と言えば、しっかりゲームを終了できるようになりました。
こうした習慣は、自己コントロール力や生活リズムを整える力にもつながります。
ただ与えるのではなく、“親子で一緒に楽しみながらルールを学ぶ”ことができるのが、推し活の魅力でもあるのです。
夫婦や家族で協力して、遠征もOK|子連れでも推し旅はできる!
もちろん、遠征やイベント参加となると、金銭面や移動のハードルもあります。
でも、家族で協力しながら「子連れ推し活・子連れ推し旅」をすれば、忘れられない思い出が生まれます。
- 夫婦で「推し育」を共有する
- 子どもが小さい時期にこそ、一緒に遠征するチャンスを活かす
日常では得られない体験を、“推し活”を通じて家族全員で楽しんでみてはいかがでしょうか?
まとめ|子連れ推し活は親子の絆を深める最高の育児方法
- 子どもは親の“好き”から学び、育つ
- 親子で共通の趣味があると、会話・思い出・学びが増える
- 推し活は、家庭でできる最高の情操教育
子どもが小さいうちにしかできない「一緒に楽しむ時間」を、遠慮せず“推し活”で彩っていきましょう。
おすすめ記事
ハーモニーランドについての記事まとめ

我が家の推し旅について学ぶなら
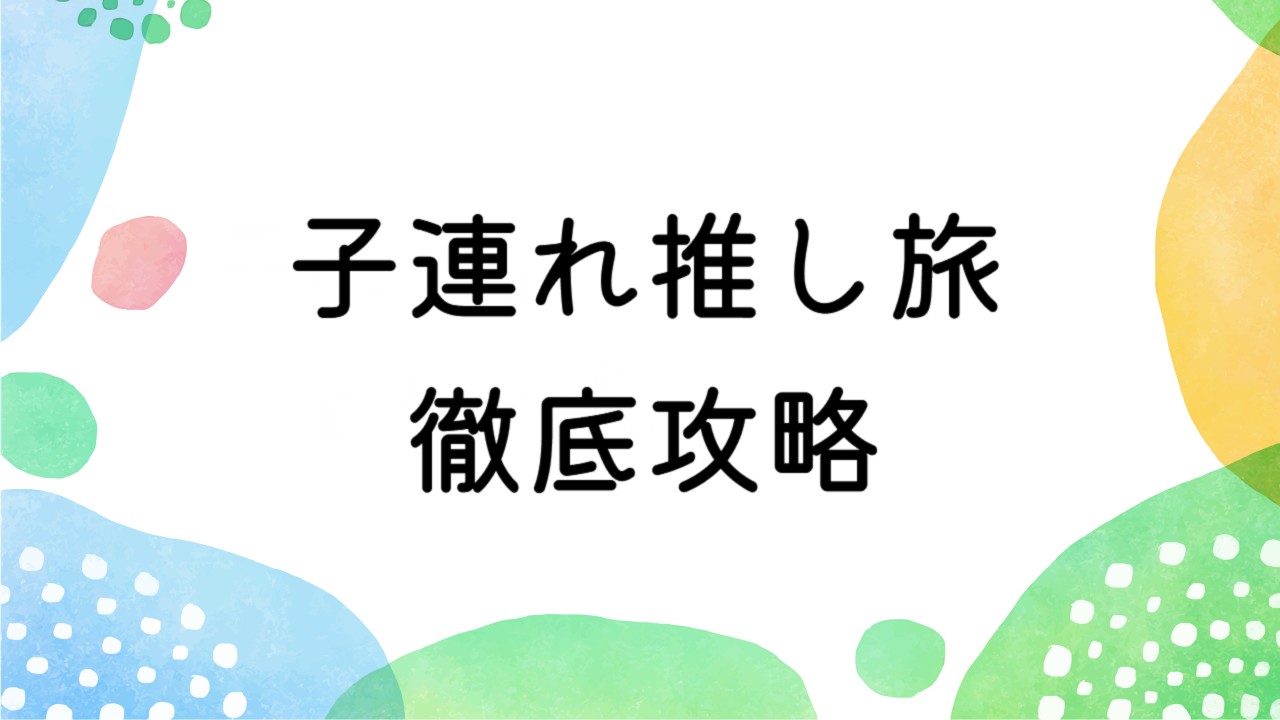
早生まれっ子には推し活がおすすめな理由
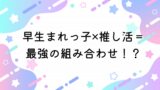
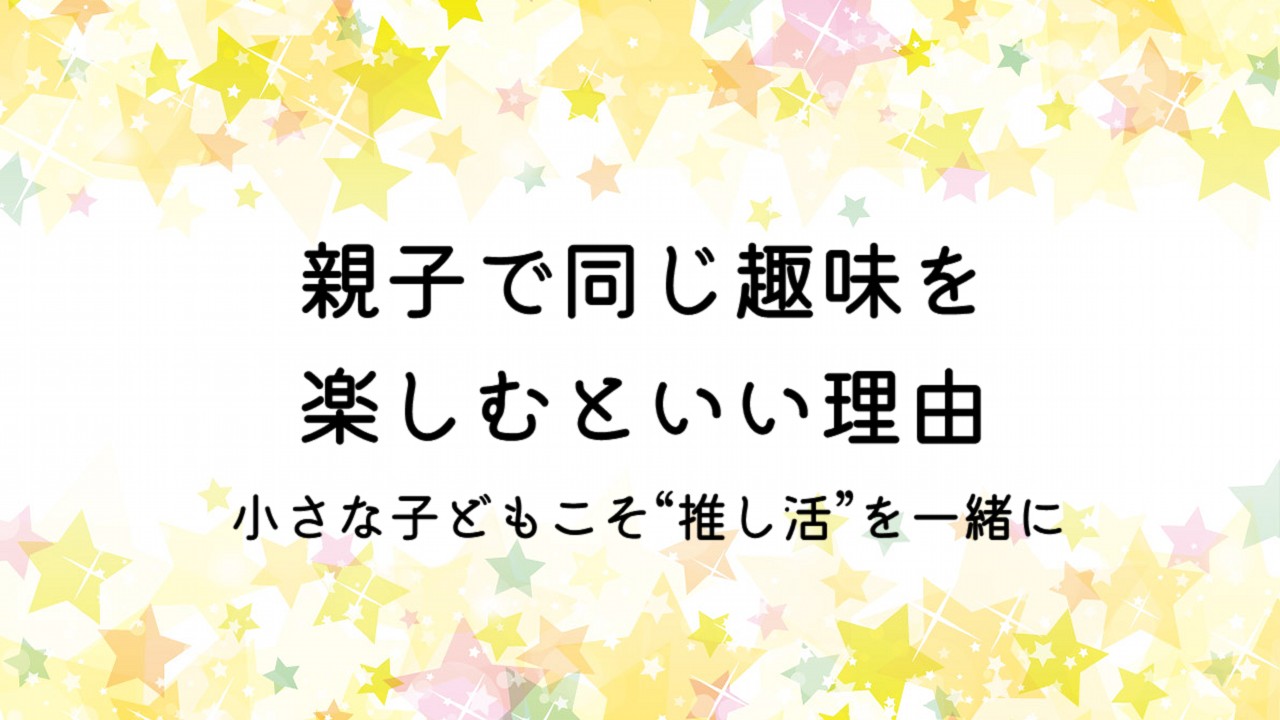
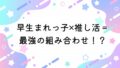
コメント